図2-1 ヒギンズ=熊谷の停滞と離陸
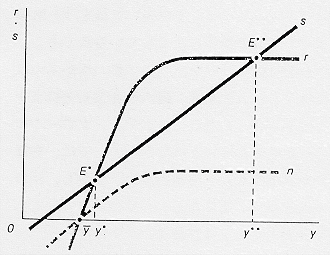
出所:福岡正夫(1997)『ゼミナール経済学入門』日本経済新聞社,533頁。[Rakuten]
第1段階は伝統的社会である。伝統的社会は産業構造が在来産業のモノカルチュアで、労働生産性も低く、経済活動の大部分が自給自足の農業生産に向けられている。これを中国に当てはめれば、すでに前章で触れたが1911年辛亥革命までとすることができる。
第2段階は離陸先行期である。経済の成長局面になる離陸の必要条件が徐々に満たされていく期間である。経済の成長局面とは具体的には1人当たりのGNPが持続的に上昇していく期間である。離陸先行期の最も大きな特徴は国民の価値観の変化であると思う。今日多くの途上国が貧困に苦しんでいる。貧困を解消するために経済成長が必要とされる。開発経済学はイデオロギーや開発理念の影響を受け、様々な価値観を内包しているが、基本的には経済成長による途上国の貧困の解消を目標としている。しかし、国民の価値観が変化せず伝統的な社会にとどまろうとするならば、経済成長はできないし、貧困も解消されない。蛇足になるが、経済開発は、その目標とは裏腹に失敗すれば、低開発ながら安定していた社会を不安定にしてしまうかもしれない。
W.W.ロストウがあげている離陸先行期の特徴は、その他に農業技術の改良、家内手工業、商業、サ−ビス業の拡大、貯蓄意欲が増大し企業家が台頭すること、教育の普及などがある。これも中国に当てはめれば前章で触れたように1911年辛亥革命から1951年までとなる。国民の価値観について更に検討すると中国はいくらか特殊性がある。一般的には辛亥革命を担った革命家の啓蒙活動と社会変革によって人民が徐々に国民的な意識を持つようになったということができるだろう。しかし、先ほど指摘した離陸先行期は中国が半植民地化されていた時期にほぼ当てはまる。ここでも民族資本の概念である程度説明できるだろう。つまり、自立的な国家建設のための自立的な経済建設である。中国では経済成長のために必要な価値観の変化がナショナリズムに触発されて起こったのではないだろうか。これは中国だけに限らないが、その後の経済成長に大きな影響を与えた。農業技術の改良、教育の普及といった要素に関しては手許に資料がないのでここでは言及しない。
第3段階は離陸期である。離陸期になると貯蓄率と投資率が急速に高まり、1人当りGNPは持続的な上昇を開始する。W.W.ロストウは離陸期の特徴を3つあげている。1つめは投資率が5%以下から10%以上に増加することである。2つめは主導産業があらわれ他の産業部門の成長を誘発することである。3つめは経済成長を持続するための政治的、社会的、制度的な枠組が成立することである。これら3つの判定基準にもとづいてW.W.ロストウは中国の離陸期は1952年から始まったと推定している。本論では中国の離陸期に関してW.W.ロストウの推定を尊重する。しかし1人当りGNPの持続的な上昇という点を重視するといささか結論が異なってくる。
第4段階は成熟化の時代である。離陸期のあとにくる波動を伴う長い進歩の時期である。特徴として、近代的産業技術が全分野に広がり、主導産業が重化学工業になる。また産業構造は第2次産業に特化する。成熟化の時代に現在の中国が当てはまっているのかはっきりとしない。中国が今なお持続的な経済成長を続けていることを重視すれば未だ離陸期にあると言える。他の要素を当てはめようとしてもそのまま当てはめることができないので中国の歴史と現状は特殊であると言わざるを得ない。例えば、中国は軽工業に先んじて重化学工業が発展しているし、高い工業化率もずいぶん早く達成している。
第5段階は高度大量消費の時代である。成熟化の時代を経て、国民一般の所得水準が更に上昇すると消費構造が変化し、耐久消費財やサ−ビスに対する需要が爆発的に増大する。具体的には大衆乗用車や家庭電気機器が普及する。米国では1920年代の初め、西欧や日本では1950年代になってからである。中国の現状は第4段階成熟化の時代に当てはまらないのではないかと先ほど言ったが、中国の沿海部に目を向けると第5段階高度大量消費の時代の条件をほぼ満たしてしまう。沿海部においても大衆乗用車はまだそれほど普及していないが家庭電気機器はかなり普及している。また、中国国内の産業はこれらの大量の需要に応えられるだけの生産設備を持っている。生産能力が過剰であるためにそれが問題となっているほどである。
W.W.ロストウの経済発展段階説を簡単に解説しながらそれを中国に当てはめてきたが、現在の中国は第3、第4、第5段階の特徴をすべて持っているようである。これは前章で触れた様々な中国の特徴から生じたものである。西側諸国の経済成長の経験から抽出された経験則がそのまま当てはまらない点は中国経済の特殊性である。
経済発展段階説はドイツ歴史学派のF.リスト等によって一般に知られているが、W.W.ロストウの経済発展段階説はそれらといささか異なる。その違いとは最も関心が持たれている経済発展のための要件を明示している点である。
途上国はなぜ経済発展をすることができないのか? まず思い浮かぶのは各国の初期条件である。具体的には乏しい天然資源、輸入代替工業化政策を思い浮べれば小さな国内市場があろう。しかし、香港やシンガポ−ルの例を見れば明らかなようにそれらは致命的な障害とはならない。では、先ほど離陸のための条件で示した10%以上の投資率であろうか。しかし、経済発展をするためには10%以上の投資率が必要であることはわかっていても停滞のメカニズムが存在し、それを実現することは容易なことではない。
停滞のメカニズムの説明はいくらか長くなる。経済発展をするためには投資率を上昇させなければならない。投資率を上昇させるためには高い貯蓄率が必要であり、高い貯蓄率のためには1人当たり所得が上昇しなければならない。それでは1人当たりの所得を上昇させればよいという結論になるが、1人当たりの所得の上昇は基本的に経済発展に伴って上昇する。または1人当たりの所得を上昇させるためには高い労働生産性が必要であるが、そのためにはまた投資が必要なのである。ここまでなら投資をするための資金を借りてくれば問題は解決されるように思うが、1人当たり所得の上昇が人口の増加を誘発するというTh.R.マルサス的人口法則が作用し、問題を複雑にする。停滞のメカニズムとはこのように複雑である。
停滞のメカニズムをふまえた上で離陸のための条件を示せば、まず資金を調達し、投資する。その国が離陸先行期の条件を満たしていれば、投資によって経済がいくぶん成長する。その経済の成長を持続的なものとし、経済を発展させるためには、なお成長率が人口の増加率を超えなければならないということである。
このような停滞のメカニズムを理解するためには図2-1ヒギンズ=熊谷の停滞と離陸を参考とするのがいい。縦軸のrとsはそれぞれTh.R.マルサス的人口増加率分を補う必要投資率と貯蓄率である。横軸のyは1人当たり所得水準である。
図2-1 ヒギンズ=熊谷の停滞と離陸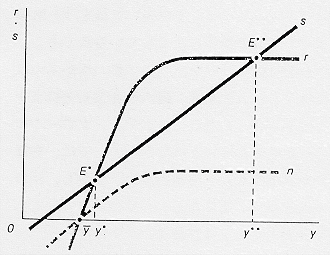 出所:福岡正夫(1997)『ゼミナール経済学入門』日本経済新聞社,533頁。[Rakuten] |
図2-1からは、停滞のメカニズムから抜ける出すためにはY**の所得水準を超える生産性の上昇が必要であることがわかる。更にr曲線の下方へのシフト、又はs曲線の上方へのシフトによってY**の水準そのものを左に移行させ、停滞のメカニズムからの脱出を容易にすることもできる。
r曲線は人口増加率nに依存している。だからr曲線を下方にシフトさせるためには人口増加率を引き下げればいい。蛇足になるが人口増加率は人道的な開発援助等で死亡率が引き下がったことにより引き上げられたので経済成長のために人口増加率を引き下げる努力をすることは戦前よりも困難になっている。中国は以前から人口抑制政策を採っている。人権問題に抵触しかねない人口抑制政策はこのような理論的な裏付けがある。人権を個人の権利から見れば人口抑制政策は個人の権利を制限するものでマイナスである。一方、人権を人間らしく生きる権利や国民福祉の増大という面から見ると人口抑制政策はやむを得ないものとなり、プラスである。中国の人口抑制政策は理論にもとづいた合理的政策である。
s曲線は貯蓄率なので上方にシフトさせるためには貯蓄性向を高めなければならない。途上国においても裕福な所得階層は存在する。しかし、この裕福な所得階層は余分な財力を貯蓄せずに消費してしまう傾向がある。貯蓄もタンス預金では意味がなく、金融機関に預けられなければ投資に回らない。図においてs曲線は貯蓄率を表し、貯蓄率=投資率が仮定されている。更に、高い投資率が経済成長をもたらすためにはその投資が労働生産性の上昇を伴う投資でなければならない。これらの過程を実現するためには銀行制度を始めとする金融組織の整備が重要である。
中国経済は高い貯蓄性向を持ち、現在は少なくとも離陸期に入っている。よって、貯蓄性向を高める点に関してはあまり当てはまらないかもしれない。しかし、貯蓄率=投資率にするための努力は続けられなければならない。
はじめに 第1章 中国経済の特徴 第1節 比較体制論と経済開発論 第2節 中国の経済史概略 第3節 巨大な国土と人口 第2章 開発経済学のアプローチ 第1節 工業化政策 第2節 W.W.ロストウの離陸 第3節 二重経済発展モデル 第3章 農村における近代的工業部門 第1節 郷鎮企業の発展過程 第2節 郷鎮企業の統計分析 おわりに 参考文献 |